みなし残業代制度を導入する場合の留意点~最高裁令和5年3月10日判決を踏まえて~

労働基準法第37条は、時間外労働の長さに応じた割増賃金を支払うことを求めています。
近年、割増賃金をあらかじめ定額として設定して支給する、いわゆる「みなし残業代制度(固定残業代制度)」を採用する企業が多くなっていますが、その適法性は、これまで度々、裁判所において争われてきました。
そうしたなかで、令和5年3月10日に、最高裁は、割増賃金という名目で支払われていた金額について、そのうちに、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分を相当程度含んでいるものと解さざるを得ないとして、労働基準法第37条に基づく割増賃金が支払われたものとはいえないと判断しました(最高裁第二小法廷令和5年3月10日判決・労働判例1284号5頁。以下「令和5年判決」といいます。)。
令和5年判決の事案では、割増賃金名目で支払われていた金額のうちに、実際の時間外労働時間に基づいて労働基準法第37条に従い算定された金額が含まれていましたが、最高裁は、その労働基準法第37条に従い算定された金額部分も含めて、割増賃金該当性は認められないとしている点が注目されます。
本稿では、令和5年判決における事案の概要と判示の理由を概観し、適法なみなし残業代制度を導入するための留意点を解説します。
1 令和5年判決以前の判例の状況
労働基準法第37条は、政令で定められた一定の比率に基づく割増賃金の算定方法を定めています。
そのため、定額のみなし残業代制度を設ける場合には、労働基準法第37条所定の方法とは異なる方法で割増賃金を支払うことになります。
裁判所は、従来、労働基準法第37条所定の方法以外の方法で割増賃金を支払うことも、直ちに違法になるわけではないとする一方で、労働基準法第37条所定の方法以外の方法で割増賃金を支払う場合には、以下の二つの要件を満たす必要があるとしてきました。
|
2 令和5年判決の事案の概要
令和5年判決は、トラック運転手として勤務していた労働者(以下「X」といいます。)が、一般貨物自動車運送事業等を営む株式会社である使用者(以下「Y」といいます。)に対し、時間外労働、休日労働及び深夜労働(以下「時間外労働等」といいます。)に対する賃金並びに付加金等を請求した事案に関するものです。
令和5年判決の事案(以下「本事案」といいます。)においては、以下のような事情がありました。
- XがYと雇用契約を締結した当初、Yにおいては、Yが従業員の運行内容(出発、輸送、積込、帰庫)等に応じて月ごとの賃金総額を決定したのち、その総額から定額の基本給と基本歩合給を差し引き、残額を時間外手当として従業員に支給する、という賃金体系(以下「旧賃金体系」という。)が採用されていた。このような賃金体系は、当時のYの就業規則に基づかない、Yの独自の計算によるものだった。
- Yは、平成27年5月に、労働基準監督署から、労働時間を適正に把握しているとは認められない状況にあるとして、適正な労働時間管理を行うよう指導を受けた。
- Yは、上記の指導を踏まえて、平成27年12月に、就業規則を変更した。
- 新たな就業規則に基づく賃金体系(以下「新賃金体系」という。)において、Yは、旧賃金体系と同様に、運行内容等に応じて月ごとの賃金総額を決定したのち、当該賃金総額から、定額の基本給等(基本給、基本歩合給、勤続手当等の総称。以下「基本給等」という。)と労働基準法第37条に従い算定した時間外手当(残業手当、深夜割増手当及び休日割増手当の総称。以下「本件時間外手当」という。)を差し引いた残額を、「調整手当」という名目で支給していた。その上で、時間外手当と調整手当を合計した金額を、「割増賃金」(以下「本件割増賃金」という。)という名目で支給していた。
<新賃金体系における賃金総額の内訳(イメージ)>賃金総額 基本給等 本件割増賃金 基本給、基本歩合給、勤続手当等 本件時間外手当 調整手当 - 本件割増賃金の総額の算定方法は、就業規則には明記されていなかったが、本件割増賃金の総額は、賃金総額から基本給等の合計額を差し引いて算出されていた。
- 旧賃金体系と新賃金体系において、Xを含むYの従業員の給与の総額や総労働時間はほとんど変わっていなかった。
- XのYに対する請求の対象となった19か月間(以下「本件請求対象期間」という。)における本件時間外手当の総支給額は約170万円だったのに対し、調整手当の総支給額は、それを上回る約203万円だった。本件請求対象期間におけるXの1か月当たりの時間外労働等は、平均80時間弱だった。
- 新賃金体系において、基本給等のみが通常の労働時間の賃金であるとすれば、Xの通常の労働時間の賃金の額は、1時間当たり平均約840円(※筆者注:これは、令和5年度地域別最低賃金額における全ての地域の最低賃金時間額を下回る金額です。)となる。一方、旧賃金体系における通常の労働時間の賃金は、1時間当たり平均約1300円~1400円であった。
3 令和5年判決の判示の理由
令和5年判決は、従来の判例において示されてきた、労働基準法第37条に基づく割増賃金該当性が認められるためには「対価性」と「判別性」要件が必要となる、という枠組みを踏襲しています。
その上で、令和5年判決は、本事案で、本件割増賃金全体について、「対価性」及び「判別性」の要件はいずれも満たされていないとし、割増賃金該当性を否定しました。
その論理は、以下のようなものです。
- 仮に、本件割増賃金が、真に時間外労働への対価として支払われていたと仮定すれば、通常の労働時間の賃金に当たる部分の額は、1時間当たり約840円となるが、旧賃金体系における通常の労働時間の賃金に当たる部分の額は、1時間当たり1300円~1400円程度だったから、新賃金体系における給与水準は、旧賃金体系における水準から大きく減少する。
- 本件請求対象期間におけるXの1か月当たりの時間外労働等は、平均80時間弱だったが、これを前提として算定される本件時間外手当を上回る水準の調整手当が支払われていた。したがって、本件割増賃金が真に時間外労働等に対する対価として支払われていたと仮定すれば、実際の勤務状況からは想定し難い長時間の時間外労働等を見込んだ過大な割増賃金が支払われていることになる。
(※筆者注:前記2(7)のとおり、本件請求対象期間にXに支払われた調整手当の支給総額は、本件時間外手当の支給総額を上回っていました。したがって、「本件割増賃金」として支払われていた金額のうち、実際に生じた時間外労働に対応する金額は5割以下であり、5割以上を調整手当が占めていたことになります。すなわち、「本件割増賃金」は、実際に生じた時間外労働の2倍以上の時間外労働に相当する金額となっていました。この点を捉えて、裁判所は、上記下線部のように評価したと考えられます。) - 賃金体系の変更による1、2のような変化について、Yから、Xを含む労働者に対して、十分な説明がなされたともうかがわれない。
- 以上の諸事情を考慮すれば、新賃金体系は、Yが独自に算定した賃金総額を超えて割増賃金を生じさせないようにするべく、旧賃金体系においては通常の労働時間の賃金として支払われていた賃金の一部を、名目のみ本件割増賃金に置き換えて支払うものといわざるを得ない。
- したがって、本件割増賃金は、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分を相当程度含んでいると解さざるを得ない(対価性の要件の充足を否定)。そして、本件割増賃金のうち、どの部分が時間外労働等に対する対価に当たり、どの部分が通常の労働時間の賃金に当たるかを判別することはできない(判別性の要件の充足を否定)。
4 令和5年判決の判示のポイント
以上のとおり、令和5年判決は「本来、通常の労働時間の賃金として支払われるべき金額が、名目上、時間外労働等に対する対価として支払われている」という点に焦点を当てています。
もし、通常の労働時間の賃金として支払われるべき金額を、名目上、時間外労働等に対する対価として支払うことを認めるならば、使用者は、賃金総額を引き上げることなく、極めて長い想定残業時間を念頭に置いたみなし残業代制度を設けることができることになり、平均的な時間外労働時間を大幅に上回るレベルの時間外労働を、追加で対価を支払うことなく行わせることが可能になります。
しかし、そのような事態は、まさに、時間外労働等を抑制するとともに労働者への保証を実現しようとした労働基準法第37条の趣旨に反するものとなります。令和5年判決の根底には、そうした懸念があると理解することができます(草野耕一裁判官の補足意見参照)。
また、令和5年判決の原審及び第一審は、本件時間外手当と調整手当について別々に対価性・判別性の要件を検討し、調整手当についてのみ対価性・判別性の要件の充足を否定したのに対し、令和5年判決は、本件時間外手当と調整手当を合わせた本件割増賃金全体について、対価性・判別性の要件を検討し、本件割増賃金全体について、対価性・判別性の要件の充足を否定しました。
本事案における調整手当は、本件割増賃金から本件時間外手当を控除することで当然に算出される額であって、独立した算定式を持つものではありませんでした。
令和5年判決は、このことに着目して「時間外手当と調整手当とは、手当の名称を分けているのみで、両者の区別にそれ以上の実質的な意味を見出すことはできない」として、本件割増賃金全体について対価性・判別性を検討したのです。
このような令和5年判決の判断枠組みからは、たとえ労働基準法第37条に従い算定した手当を支払っているとしても、賃金体系によっては、当該手当について割増賃金該当性が認められない場合があるといえます。
さらに、原審及び第一審の考え方によれば、使用者が支払う未払割増賃金は、調整手当のみを基礎賃金として算定すればよいこととなりますが、令和5年判決によれば、使用者は、本件割増賃金の総額を基礎賃金として算定した割増賃金を支払わなければなりません。
5 みなし残業代制度を導入する場合の留意点
令和5年判決は、従前の裁判所の判断基準を踏襲しており、新たな一般論を示したわけではなく、事案に即した事例判断にとどまると評価されています。
もっとも、以上に見たような令和5年判決の事案と判断理由からすれば、みなし残業代制度を導入する場合には、特に、従前の賃金体系を変えて、1時間当たりの賃金が減るような場合を中心に、以下の点に留意する必要があるといえます。
|
また、当然のことながら、1時間当たりの賃金が最低賃金を上回る必要がある点にも留意しなければなりません。
6 最後に
令和5年判決を含む従来の判例は、当該事案における賃金体系や勤務実態を個別具体的に認定した上で、対価性・判別性の有無を判断し、結論を導いています。
したがって、みなし残業代制度の適法性を判断するには、個々の企業における実情を踏まえた個別具体的な検討が必要です。
みなし残業代制度の導入を検討される際には、弁護士を含む専門家による助言を受けることをおすすめいたします。
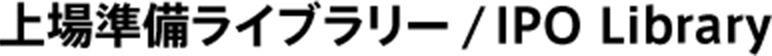
 S&W国際法律事務所
S&W国際法律事務所




