投資契約書や株主間契約書に規定された株式買取請求権を考える

今回は、とてもマニアックなテーマです。
日本の投資契約書や株主間契約書には、必ず株式買取請求権が規定されています。
今回は、この株式買取請求権について、深く掘り下げます。
目次
1 株式買取請求権の意義
なぜ、投資契約書や株主間契約書に株式買取請求権が定められているのでしょうか。
それは、投資契約書や株主間契約書に定められた規定に違反した場合のサンクション(制裁)として必要な規定だからです。普通の契約であれば、解除権や損害賠償請求権がサンクション(制裁)として定められていますし、仮に定められていなかったとしても、民法に基づき、解除権や損害賠償請求権が発生する場合が多いです。
しかし、投資契約書や株主間契約書に定められている規定は、解除権や損害賠償請求権が上手く機能しないことがほとんどです。
例えば、事前承諾事項について考えてみましょう。
事前承諾事項とは、発行会社が、新株発行等の予め定められた項目について意思決定をする場合に、その前に投資家(いわゆるリードVC等の一部の投資家であることも少なくありません。)に通知し、投資家の事前の承諾がなければ、意思決定をしてはならないという規定です。
発行会社が事前承諾事項を破った場合、要するに、投資家に通知をせずに、又は事前に承諾を得ずに、新株発行等の予め定められた項目についての意思決定をした場合です。このような場合に、解除権や損害賠償請求権は、機能しないのでしょうか。
まず、解除権ですが、投資家が解除を望むということは、投資直前の状態である新株発行前の状態に戻してほしい、すなわち、株式は要らないので投資した金額を戻してほしいということになります。
ここで問題となるのは、発行済み株式の取り扱いです。発行済みの株式は、募集株式の引受契約が完了したことにより、有効に発行された有価証券ですので、発行後の事情により、遡及的になかったことにはできません。そのため、発行済みの株式を発行されなかったことにはできず、新株発行前の状態に戻すということができません。
また、損害賠償といっても、投資家に通知をせずに、又は事前に承諾を得ずに、新株発行等の予め定められた項目についての意思決定をしたことによる「損害」とは何か、そしてその「損害」の額とはいくらか、といった問題があります。
履行利益という考え方をとると、もしそのような意思決定をしなかった場合と比較して被った損害を検討する必要がありますが、その差分がいくらかというのは、よくわかりません。簡単に算出できるものではなく、立証も容易ではありません。
このように解除権も損害賠償請求権も上手く機能しないために、別の形で、サンクション(制裁)を設ける必要があります。その必要から投資契約や株主間契約上に設けられたものが、株式買取請求権です。
株式買取請求権は、解除権とは異なる権利ですが、解除権に近い結論、すなわち、契約違反等が生じた場合に、株式を投資家の手元から無くすとともに、その株式の価値と同じ価値の金銭を投資家に戻す権利として設計されています。
2 どのような場合に株式買取請求権を発動させるか(株式買取請求権の要件)
株式買取請求権がどのような場合に生じるかについては、以下のものが定められていることが多いです。
- 契約違反(催告後一定期間内に是正しない場合)
- 表明保証の内容が真実又は正確でなかった場合
- 払込の前提条件が充足されていなかったことが判明した場合
- 株式上場の要件を充足しているにもかかわらず、合理的な理由なく上場しない場合
- 取締役が企業価値を毀損する重大な行為をした場合
- 支配権が変更された場合で、投資家の事前の同意を得ていない場合
実際に、1から4までは、ほとんどの投資契約で規定されているように思います。5や6は、1に含めることができることも多いので、定められていないことも少なくありません。
ほかにファンド満期の到来などが定められているケースもないわけではありませんが、これは一般には発行会社にとっては受け入れられないでしょう。
3 株式買取請求権が発動するとどうなるか(株式買取請求権の効果)
詳しく定められている場合は、投資家の請求がなされたときに、何らの意思表示を要することなく、請求を受けた発行会社、経営株主又は第三者が請求のあった数の発行会社株式等を買い取る義務を負うこととされ、その譲渡金額は、5~6種類の算定方法(詳しくは、「5 譲渡金額の算定方法」へ)のうち最も高い金額と定められています。
ただ、発行会社は、契約上買取義務があるとしても、強硬法規である会社法が優先されます。会社法では、自己株式の取得について、財源規制と手続規制がありますので、これらの規制をクリアできなければ、買取義務を履行できません。
そのため、株式買取請求権の規定では、経営株主も買取義務を負うこととされていることがほとんどです。
4 投資家は、行使した株式買取請求権を撤回することができるか
行使した株式買取請求権を撤回ができるか否かについて、契約書に詳しく定められていない場合、問題が生じることがあります。特に、行使したものの、発行会社や経営株主が対価を支払わない場合や支払う前の期間に、撤回できるのか、議決権行使ができるのか、といった問題が生じます。
単に株式買取請求権が定められている場合に、その権利を行使する旨の意思表示が到達すると、自動的にその権利の効果が発動しなければ意味がありません。そして、買取義務者として定められている発行会社と経営株主個人に、拒否権はなく、改めて契約の条件をやり取りする余地はありません。
となれば、株式買取請求権を行使する意思表示の到達と同時に売買契約の効果が発動することになりますので、民法上は売買の予約(民法第556条第1項)にあたり、株式買取請求権は停止条件付予約完結権といえるでしょう。
株式買取請求権を行使する意思表示の到達と同時に、売買契約の効果が発動している以上、少なくとも当事者間では、有効であり、(特に契約で撤回できる旨が定められていなければ)撤回はできないものと考えざるを得ないでしょう。
但し、経営株主らが対価を支払わない場合に不履行があるとして、株式買取請求権の意思が到達することによって生じた売買契約を解除する余地はあると思われ、この解除は、撤回と同じ効果が生じます。
5 譲渡金額の算定方法
譲渡金額は、以下のうち、最も高い金額と定められることが多いです。
3と4はよく似た発想の算定方式であり、ほとんどの場合、3は4以下の金額になりますので、3か4はいずれか一方のみが定められて、5つの場合も多いです。
- 当該投資家が本条に基づく買取請求の対象となった株式を取得した際の1株当たりの払込金額
- 財産評価基本通達に定められた「類似業種比準価額方式」に従い計算された1株当たりの金額
- 発行会社の直近の監査済貸借対照表上の簿価純資産に基づく発行会社の1株当たりの純資産額
- 発行会社が解散し、かつ発行会社の直近の監査済貸借対照表上の簿価純資産が残余財産であると仮定した場合に、当該株式1株に分配されるべき金額
- 発行会社の株式の譲渡事例又は増資事例(潜在株式の付与又は発行を含む。)における1株当たりの譲渡金額又は株式発行価額(潜在株式の場合には、その発行価額及び行使価額に基づき、1株当たりの株式発行価額として当該投資家が合理的に算定する金額)。
- 当該投資家が選任した第三者の鑑定による発行会社株式等の1株当たりの公正な時価
「最も高い金額」ですので、かなり投資家に有利であり、経営株主にとっては重たい規定です。ただ、サンクション(制裁)の条項であるだけに、不合理ともいえないと思います。
6 株式買取請求権でよく定められている事項
株式買取請求権でよく定められている事項には、次のものがあります。
- 株式譲渡に必要な手続きを履行する義務(株券発行会社の場合の株券交付、譲渡承認決議)
- 発行会社と経営株主の連帯債務関係の詳細
- みなし配当課税相当額を控除しないこと
- その他の手続への協力義務
7 残された課題
ここからは、完全な私見であり、まだまだ考え中の部分ですが、少し感じているところを記します。読者の方で、これらの課題に知見がある方は、お伝えいただけると嬉しいです。
というのも、株式買取請求権の規定には、突き詰めて考えると、まだまだ残された課題があるように思います。
〔その1〕投資家は、契約違反や表明保証違反等の事実に気付いた後、いつまでも株式買取請求権を行使可能なのか。
通常の債権の時効と同様に5年間は可能と考えられます(民法第166条第1項第1号)。ただ、株式買取請求権の発動事由があると知りつつ、それを放置し、株価の上昇と株式の現金化の良いとこ取りをしようとして、あえて行使しない場合や、保有する株式を第三者に譲渡した場合にまで、権利濫用論などで行使が止められる可能性は否定できないように思います。特に、株主となった日から1年を経過した後、又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しができないとする会社法第211条第2項に鑑みると(表明保証違反の事実に気付いた場合に近い)、契約違反や表明保証違反等の事実に気付いた後、株式買取請求権を行使せずに、議決権等の株主権を行使した後は、株式買取請求権を行使することが権利の濫用であると判断される可能性は、否定しきれないように思います。
〔その2〕発行会社と経営株主の連帯債務関係において、発行会社が買い取る場合、経営株主は連帯保証関係になるのか。仮に連帯保証になると契約書に明記した場合は、極度額を示さなければ無効ではないか。
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって、保証人が法人でないものを「個人根保証契約」といいます(民法第465条の2第1項)。株式買取請求権が行使され、発行会社が買い取るとなった場合の金銭債務について経営株主が保証することとなる契約は、保証人となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するのかがはっきりしない契約ですので、この個人根保証契約に該当すると考えられます。とすると、極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効ですので(同条第2項)、発行会社が買い取るとなった場合の金銭債務について経営株主が保証することとなる契約は、極度額の定めがなければ無効になる可能性があると考えます。そのため、実効性を持たせる場合には、具体的な極度額を明記したほうがよいでしょう。
8 まとめ
投資契約書や株主間契約書のサンクション(制裁)として定められる株式買取請求権は、投資家にとって、最終手段であり、現実に行使されることは稀でしょうし、その効果の大きさから安易に行使されるべきものでもありません。VCにとって、株式買取請求権を発動する事態は、投資の失敗であり、失敗した投資先からの回収にどれだけのエネルギーを割くことが合理的かといったマネジメントの問題もありそうです。
ましてや、争訟が裁判所に係属することになり、判決として判断を仰ぐことになる事例は、ほとんどないと思われ、本邦の判決において株式買取請求権に触れられたものはほとんどありません。
本稿が投資契約書や株主間契約書の規定の検討の一助となればと思います。
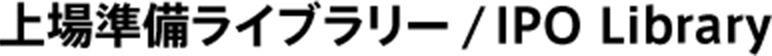
 S&W国際法律事務所
S&W国際法律事務所


